以前の投稿から2か月たっちゃいました。
この2か月は自分にとっても大事な時間だったと思います。
これまでの進め方と、これからやろうとする進め方
一番大きな進展としては、「生物学の研究の進め方」がやっと、博士課程2年目にしてわかったかもしれないということです。これまでの自分の研究(と思っていたもの)の進め方は以下の通りです。
・気になる現象について先行研究を探して、つっつけそうな重箱の隅を探す
・それに関する実験系(例えばストレス処理系)を立ち上げる
・予備実験的な10サンプル以下の実験を行う
・定性的に結果をながめて、「こんなかんじかー」という。
・たいていそのくらいのタイミングで何か(例えばゼミでボロボロに言われるとか)、心にダメージを負うことが起きる
・再起動の時間。
・「よし!違うことやろ」
(以下、無限ループ)
もちろんそれらに通底する一番の興味はあったのですが、それに対してどう切り込んでいいのかわからず、このようにフラフラといろいろなものにちょびっと触ることを繰り返してきました。
それでいて「自分は研究できないんだ」とげき病みする日々。
そりゃ研究できるわけないよ。もっといえば、定量的なデータを出して、研究を進めることできないよ。だって、決めたテーマについて「何を明らかにするのか」「どうやるのか」「科学的に物事を言うのに必要なサンプル数はいくつか」が定まっていないし、粛々と続けるべき実験ができていなかったのだから。
これからするべきことは
・実験ごとの目的をしっかりと定めて、それを明らかにすることを第一に考える
・定量的なデータとして扱える測定項目を考える(指導教員に相談しながら)
・サンプル数を10以上用意する
・実験を継続して行う
・データを統計などで客観的にきちんと扱う。
だと思います。
たぶんわかってる人からしたら「お前今更そんなこと言ってんのかよ」という内容だと思うのですが、自分はそれに気が付くまでに3年以上かかりました。卒論を入れたら4年以上か。
それに今木が付けたのは、今の自分の現状をかなり見かねた先輩(ポスドク)が丁寧な指導をしてくれたからです。指導教員もいますが、なんというか「先生が思っている僕の現在地」と「実際に僕がいる現在地」にズレがあって、的確な指導がなされていなかったと感じます。そこのギャップを考慮して、そこを埋めるにはどうするべきなのかを教えてくれたのが先輩でした。入口までは先輩が導いてくれたのだから、後はやるべきことを淡々とこなすだけだと思います。
今はいろいろと実験の準備をしています。簡単な実験だけど、未報告の内容。バラツキが大きそうだからサンプル数を多めにしていざ勝負!
—
もし今、昔の自分に何かを伝えられるなら?
ちょっと反省タイム。
どうしたらもっと早く軌道に乗れていたのか。それを考えて、昔の自分に伝えるように、少しまとめてみました。指導教員とか先輩がずっと言っていてくれたことですね。受け取れていなかったことがマジで恥ずかしい…。
1.もっと先行文献を「生き物のことを考えながら」読め
面白そうなことに飛びつくんじゃない!!
それはそれでいいけれども、生物学をやるのなら、「その生き物を知る」ことを一番に考えないといけない。何らかのストレスを与えることでつっついて、何かを測るだけじゃ、「生き物を知る」ことにならないからな。その生き物がどういう風に生きているのかを知ろうとして、先行研究はストレスを与えているんだから、そのことを忘れちゃいけない。
一番大事なのは、「生き物を知ろうとすること」だぞ。
2.生き物のことを考えて行った実験だったら、外野の意見も気にならないから
ゼミとかやるたびに反応悪いし、悩んだよな。それはわかる。
でもな、自分の内容は生物学をやってないから、みんなそういう反応だったんだと思うぞ。
対象生物のことを知るために、明らかにしたいことを考えて、それを確かめる実験をしていたのなら外野の意見は気にならなかったはずだ。
自分でも研究を進める方向に確信を持てていなかったから、他人(指導教員以外の教員など)の意見でグラついてたんだよな。
3.研究のための研究をしろ
何のために研究してるんだ?生き物を知るためだろ?
でもどうだ、データ(のようなもの)やグラフを「XXゼミ」「XX学会」と発表することごとにまとめてただろ。
それは、「発表のための研究のようなもの」であって「研究のための研究」じゃない。
発表のこととか考えずに、研究のために研究してくれ…。
そしたら自然とフォルダ分けも「XXのYYの影響」とかになるはずだから。最近はそうなったな。
4.サンプル数を増やすことを面倒くさがるな
わかるよ、個体数が増えると観察とかいろいろ時間かかるよな。できれば最小限、n=3とかにしたくなるよな。でもそれじゃだめだ。バラツキが大きいのは薄々思っていたんだから、もっともサンプル数を増やす方向に早く舵を切るんだ。
タイパを求めて、ごみデータが出ていたら世話ないぞ。
必死で、真剣に、研究をしたいのなら、目先の労力のことを気にしちゃいけない。とにかくサンプル数を増やすことが一番大事だ。
5.生物学は地道な作業の積み重ねだ
PCの前に座ってデータのように見えるごみデータをいじくることに時間を使うな。データをちゃんと出すんだ!!地道に観察して、地道に数を数えて、地道に測定をするんだ。
もちろん画像解析とかで自動化できることは自動化することを目指してもいいけれど、それにこだわりすぎるな。場合によっては画像の撮り直しとかももっと早くに検討しろ。
頭をひねってパパっとできることなんて何もない。きっとデータの解析も地道な作業の積み重ねだ。
時間と体力を使うことを惜しむんじゃない!
ゴミはいくらいじくってもゴミでしかないんだから。もちろん予備実験として割り切って少ないサンプルで行ったのなら、そこからサンプル数を増やして本実験をすぐにやるんだ!予備実験データで何かを言おうとするんじゃないよ。
たぶん、生物学のことがわかっていなくいても、4,5ができていればデータだけはあって、それをいじくることができていただろうに…。今からじゃオーバードクターになりそうだぞ。
でも、やるって決めたんだから、学位取得or「もう無理だ」って思うところまでやりきろう。

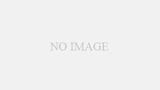
コメント